Food
Health
Specialist
ハーブ
健康学Q&A
栄養学
2018.04.10
健康学Q&A NO.4 脳を若く保つ方法はありますか?
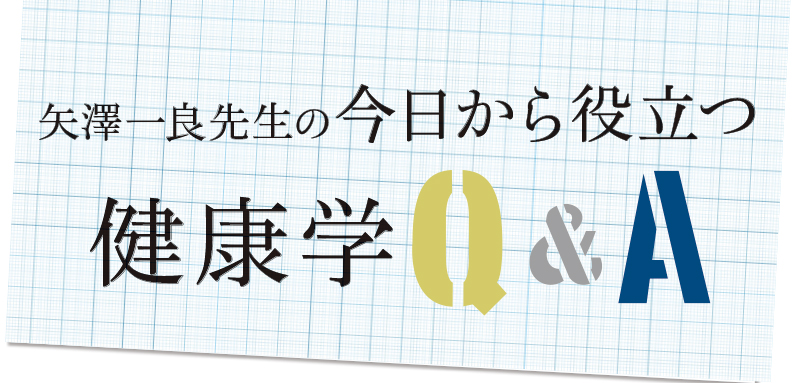
体の健康をキープするために、今からどんなことに取り組んでおけばいい?
皆様から多く寄せられる質問に対し、矢澤先生がQ&A方式で分かりやすく解説します。




|
脳細胞の計算
1日 10万個
1年 3,650万個 10年 3億6,500万個 |
脳の老化によって起こる代表的な症状は「記憶力」「判断力」の衰えなどがありますが、それは元々備わっていた脳細胞が減っていくことで起こります。そもそも脳は、体のあらゆる部位のなかでもっとも大食漢です。脳のエネルギー消費量は全体のおよそ1/4、酸素消費量は全体の半分と言われており、たとえば、朝ご飯を抜くと、午前中ぼぉーっとしていたり、立ちくらみが起こりやすくなりますよね。つまり脳の栄養不足なんです。そうした状態が慢性化すると、脳の老化は早まります。
また、脳細胞は35歳を過ぎると1日10万個ずつ減っていくと言われています。「すごい数!」と驚かれるかもしれませんが、実は、人間の脳には120億から150億もの脳細胞があると言われており、35歳から60年生きるとしても、22億個程度しか減っていないことになるんです。これを喫煙やお酒の飲み過ぎ、ストレスなどによって活性酸素を過剰に発生させ、脳細胞が減っていくスピードを加速させると、いわゆる「認知症」になるリスクが高まるのです。

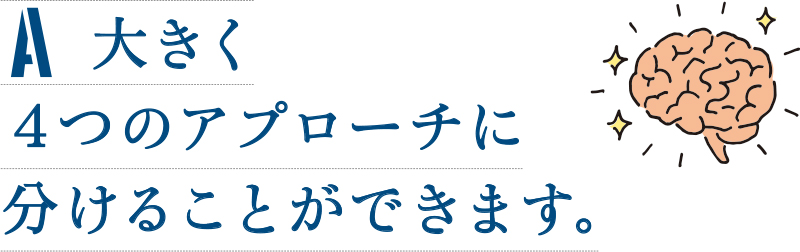
脳を若く保つということは、言い換えれば脳細胞が減っていくのを防ぐことでもあります。脳細胞が減るのを抑えるためには何が必要か、まずは4つのアプローチを知っておきましょう。
|
1.脳の血流を良くする
冒頭でもお話ししましたが、脳はカラダの中で一番の大食漢です。そのため、栄養や酸素が不足すると、低栄養状態になり脳細胞そのものの活動力が弱まってしまいます。栄養と酸素をうまく届けるには、血流を良くして栄養と酸素を効率的に供給することが必要になります。
2.活性酸素を消去する
脳に供給される酸素の一部は活性酸素となり免疫の働きを担っていますが、活性酸素は増えすぎてしまうと、外敵とは関係のない細胞まで攻撃し、死滅させてしまいます。現代人の生活は活性酸素が非常に出やすい状態にあり、日常生活や食生活を見直して抗酸化することが求められます。
3.伝達機能の維持
生きている脳細胞の働きを活性化することでも脳の老化は抑えられます。脳細胞にはシナプスとレセプターいう情報をやり取りする触手のようなものがあり、それらは加齢とともに萎縮する傾向にあります。そのため、シナプスやレセプターの動きをしなやかに保つことが伝達機能の維持、つまり脳の活性化につながります。
4.良質な睡眠をとる
脳は1日のうちに膨大な量の情報を処理しています。そのため脳を休ませてあげることも大切です。脳が休息できるのは睡眠中。しかもノンレム睡眠という深い睡眠の時のみに限られているため、良い睡眠で、疲れをとってあげることが重要です。一晩寝て、翌朝頭がスッキリしていれば問題ないでしょう。
|


脳を若く保つアプローチが幾通りもあるように、また、脳に良いと言われる栄養成分もさまざまです。こちらでは、分かりやすく表にまとめてみました。これらを毎日の食事でしっかり摂るのは大変ですので、バランスの良い食事(おすすめは和食)を意識しながら、足りない分をサプリメントで補えば問題ありません。また、完璧に摂れていないからといって気にするのも、ストレスがたまって良くありません。今日はできていなくても明日からバランスの良い食生活を心掛けようと、おおらかに捉えるくらいがちょうどいいかもしれません。
|
この記事を監修された先生

早稲田大学規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門 部門長。長年、企業や大学の研究機関で食の安全や健康食品の研究に従事。食べ物がいかに体に作用するかを分かりやすく解説。






 Members Club
Members Club



















