Health
季節の症状
2023.04.03
【特集】春の憂うつを吹き飛ばして元気に過ごす

うららかな日差しが心地よく、そこここに自然の息吹を感じる春。でも実は、この季節はうつ症状を訴える方が増える時期でもあります。その原因の多くは、心身のストレスからくる自律神経の不調。春ならではのストレス要因と対策方法を知っておけば、「春の憂うつ」も怖くありません。美しい季節を存分に楽しみましょう。
□雨の前に頭痛が起きることがある
□普段から寝つきが悪い
□暑さや寒さに無頓着
□花粉症がある
□天気予報はあまり気にしない
□転勤や異動が多い
□どちらかと言えば保守的
□NOと言えない性格
□寂しがり
□物事に慣れるまで時間がかかる
意外と多い春ならではのうつ発症リスク
うつ病は、脳の機能をつかさどる神経伝達物質のうち、精神を安定させるセロトニン、やる気や集中力を高めるノルアドレナリン、喜びや意欲に関わるドーパミンなどが不足することで発症します。神経伝達物質がうまく働かなくなる大きな原因はストレスと考えられており、本来は季節に関係なく発症するのですが、実のところ、春はうつを発症する人が増える時期となっています。
その理由のひとつが、日本の春の気候です。4月頃は日本列島を高気圧と低気圧が短い周期で通過するため、うららかな日が続いたかと思えば冷たい雨が降ったりして、寒暖差や気圧差が激しくなります。人間の体は、自律神経※の交感神経と副交感神経がバランスを取りながら体内環境を一定に保っているため、たとえば急に寒くなると交感神経を優位にして血管を収縮させ、体温が奪われないように調整します。このため、寒暖差や気圧差が激しい日が続くと自律神経が酷使され、疲弊してバランスを崩してしまうのです。これが「気象病※」と呼ばれる不調で、気分の落ち込みやイライラのほか、頭痛、めまい、疲労感、倦怠感、集中力の欠如といった症状が現れます。また、春といえば日本人の国民病とも言われる花粉症。花粉症とうつ症状とは相互に影響し合うという研究報告もあります。
こうした自然要因のほかに、春ならではの社会的要因もあります。年度末の3月と年度始めの4月は、入学、就職、異動、引っ越しなど、生活環境や職場環境に変化が生じやすい時期。これまでとは違う日常や慣れない人間関係がストレスとなり、食欲が低下する、よく眠れない、意欲が低下するといった不定愁訴が起こりやすくなるのです。特に、生真面目で責任感が強い方や、周囲に気をつかい過ぎるような方は、この傾向が強くなりがちです。
今月の注目ワード
●自律神経
体温、血圧、代謝などの働きをつかさどる神経。心と体を活発にする交感神経と、リラックスさせる副交感神経があり、双方がバランスを取って、心身が適切な状態に保たれるようコントロールしています。
●気象病
気温、気圧、湿度など天候の変化によって起きる心身の不調の総称。寒暖差や気圧差が刺激となって自律神経や内耳に作用して発症すると考えられており、国内の潜在患者数は1,000万人以上とも言われています。
女性の2人に1人以上が春のメンタル不調を経験
女性産婦人科医が代表を務めるウーマンウェルネス研究会が、首都圏在住の男女を対象に春(3月~5月)の不調に関するアンケートを行ったところ、精神面の不調を女性の55.1%、男性の46.3%が、身体面の不調を女性の68.8%、男性の59.5%が「感じる」と回答。精神的にも身体的にも半数以上が不調を経験し、男性よりも女性のほうがその割合が多いという結果に。また、主な症状としては、「気分が落ち込む」「だるさ」「疲労感」「倦怠感」「イライラする」などが挙げられています。

出典:2020年ウーマンウェルネス研究会 supported by Kao調査
食事や睡眠で脳疲労をケアし上手にストレスコントロールを
春の不調は、気候が安定したり新しい環境に慣れるにつれて回復しますが、加齢などで自律神経の働きが衰えていると、長引いて本格的なうつ病に移行したり、判断力や認知力の低下につながったりすることも。そうならないようにするには、ストレスを溜めないようにすることと、自律神経を整えることが大切です。自覚がなくても心身はストレスを感じていることが多いもの。そこで、抗ストレス作用のあるビタミンA・C・E、セロトニンの原料となるトリプトファン※を、食事やサプリで積極的に摂るようにしましょう。リラックスできる自分の時間を持つことも大切です。
また、うつ発症の引き金となりやすい脳疲労の予防・回復対策として、この時期はいつも以上に睡眠の質を高める工夫を。就寝前にストレッチをしたり、リラックスできるアロマを取り入れたりするほか、脳を元気にして花粉症予防も期待できるハチミツを入れたホットミルクを飲むのもおすすめです。
今月の注目ワード
●トリプトファン
人間の健康維持に欠かせない必須アミノ酸のひとつで、心を安定させるセロトニンや睡眠を促すメラトニンの原料です。レバー、青魚、乳製品、豆製品、バナナ、ピーナッツなどに多く含まれています。
監修:抗加齢医学専門内科医
青木 晃先生
この記事を監修された先生
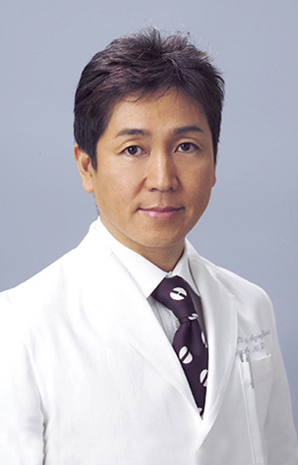
抗加齢医学専門内科医。日本健康医療学会常任理事。日本抗加齢医学会評議員。日本健康医療学会健康医療認定医。日本抗加齢医学会専門医。メディアでのわかりやすい解説に定評がある。






 Members Club
Members Club



















