Food
Health
Specialist
アンチエイジング
アンチエイジングの方程式
栄養学
2018.03.13
チーズでアンチエイジング!(その2)
チーズは優秀なアンチエイジング食品

最近の研究で、チーズが熟成する過程でできるカゼイン由来のペプチドが抗酸化的に働くことや、青カビタイプのチーズ(ブルーチーズといわれているもの)に含まれる脂肪酸が、胃がんの原因菌であるピロリ菌の増殖を抑制すること、ソフトタイプのチーズには腸内ビフィズス菌を増やし大腸がん予防の方向に働く作用があることなどもわかってきました。
機能性食品としてチーズを考えてみると、下記のような効果が期待できます。
・骨粗鬆症予防
・虫歯予防
・血糖値上昇抑制
・動脈硬化予防
・高血圧予防
・整腸作用
・胃がん、大腸がんなどのがん予防
チーズがいかにアンチエイジングに働く食品であるかがお分かりになりましたでしょうか?
チーズは種類が豊富!
さて、次はチーズの種類についてです。チーズは大きくはナチュラルチーズとプロセスチーズに分類されます。ナチュラルチーズは乳酸発酵をした後に高温での加熱処理をしていないチーズ、プロセスチーズはゴーダやチェダーなどのナチュラルチーズを原料にして、乳化剤を加えて加熱・溶解させてから冷やして固めたものです。加熱殺菌により乳酸菌や各種の酵素は活性を失っているため、長期保存が可能になります。反対にナチュラルチーズは乳酸菌が生きているため、時間と共に風味が変化するのが特徴であり魅力です(ナチュラルチーズは、フレッシュな状態を楽しむタイプと寝かせてから食べる熟成タイプのものがあります)。ナチュラルチーズは6つのカテゴリーに分類されます。
1.フレッシュタイプ:乳を凝固させてホエイを排出したらできあがり
・熟成をさせない
・水分が多く軟らかい
2.白カビタイプ:チーズ表面に白カビを繁殖させ熟成させる
・表面から内部に向かって組織が軟らかく変化する
・同時に風味が豊かに変化する
・クリームを加えて脂肪分を高めたチーズもある
3.青カビタイプ:チーズの内部に青カビを繁殖させ熟成させる
・好気性のある青カビがチーズ内部に隙間を作ったり、意図的に金串で空気穴を開けるためもろく崩れやすい
・熟成によって風味が豊かに変化する
・塩味がつよく甘口ワインに合わせることも
4.シェーヴルタイプ:山羊乳から作られるチーズ全般
・小型のものが多い
・山羊乳にはカロテンが少ないので真っ白い生地が特徴
5.ウォッシュタイプ:チーズの表面を塩水やワイン、マール、ビールなどで洗う
・リネンス菌が繁殖して粘り気のある膜をつくる
・独特な香りがでてくる
6.セミハードタイプ/ハードタイプ:長期熟成向きに作られたチーズ
・原料となるミルクの種類はいろいろ
・セミハードは外皮無しが多くハードは外皮付きが多い
・セミハードはハードよりも水分が多くしっとりしている
・ハードタイプは平野部より山地で造られる傾向
ワインと一緒に楽しみましょう

最後にワインとチーズのマリアージュについて述べておきましょう。基本的にはチーズの産地で造られているワインがおすすめです。造られていなければ、なるべく近所のワインを選びます。チーズはどちらかというと赤ワインに合います。どれか1本をという時にはフルーティーな(あまり重くない)赤ワインを選びましょう。塩味の強い(青カビタイプ)ものには酸味のあるワインや甘口ワインを合わせます。クリーミーで脂肪分の多いタイプのチーズにはタンニン(渋味)がしっかりある赤ワインがお勧めです。
1.フレッシュタイプ:スパークリングワイン、軽めの白やロゼ
2.白カビタイプ:フルーティーな赤(高脂肪のものにはフルボディの赤を)
3.青カビタイプ:デザートワイン、リースリングの甘口、フルボディの赤
4.シェーヴルタイプ:フレッシュなものには辛口の白、ロゼ
5.ウォッシュタイプ:柔和な赤、まろやかで上質な白
6.セミハードタイプ:マイルドなものには辛口の白 、やや熟成していればロゼや軽めの赤
7.ハードタイプ:バランスの取れた辛口の白、超硬質であればコクのある赤
クセの強いタイプのものでも、ワインと合わせるととても美味しく感じますよ。食わず嫌いは人生の損!チーズとワインのマリアージュを楽しんで充実のアンチエイジングライフを!
この記事を監修された先生
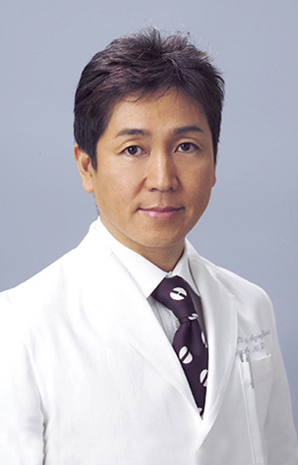
抗加齢医学専門内科医。日本健康医療学会常任理事。日本抗加齢医学会評議員。日本健康医療学会健康医療認定医。日本抗加齢医学会専門医。メディアでのわかりやすい解説に定評がある。






 Members Club
Members Club
























