Health
Specialist
健康学Q&A
栄養学
2018.02.20
健康学Q&A NO.2 疲れが抜けないのはナゼ?
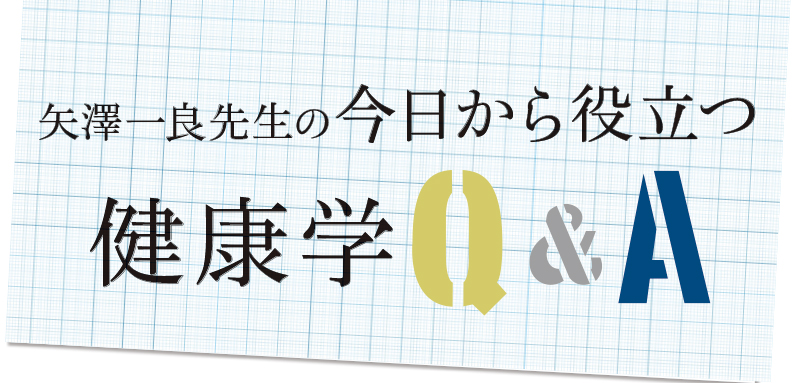
体の健康をキープするために、今からどんなことに取り組んでおけばいい?
皆様から多く寄せられる質問に対し、矢澤先生がQ&A方式で分かりやすく解説します。
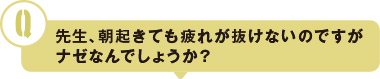
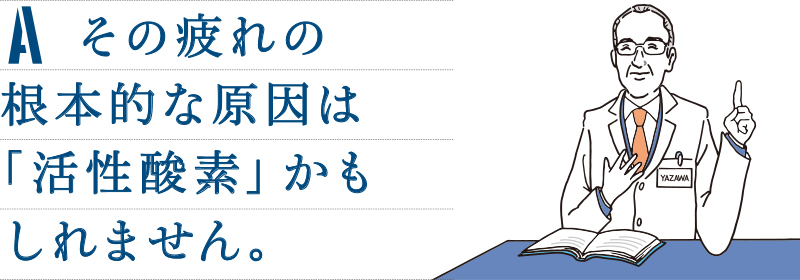
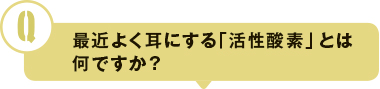
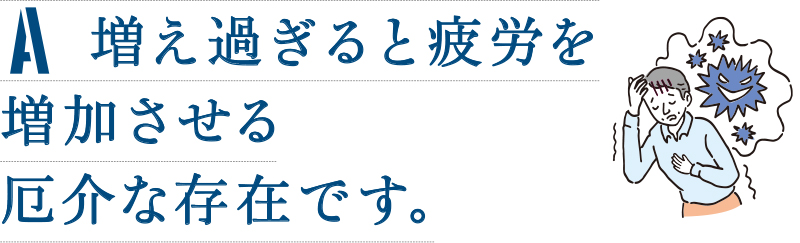
以前は「乳酸」が疲労物質と言われていましたが、実はそうではなく乳酸もエネルギーとして使われることが分かっています。
では、“疲労を引き起こす本当の犯人は誰か?”と言うと、筋肉の細胞の破壊、あるいは機能を低下させる「活性酸素」です。活性酸素はその名の通り活発な酸素で体を酸化させる力が強く、疲労だけでなく、老化や病気の根本的な原因にもなります。喫煙、過度な飲酒、運動不足、ストレス、激しいスポーツなどによって必要以上に発生しますが、生活習慣の見直し、食生活の改善によって抑えることができます。
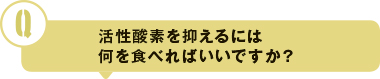
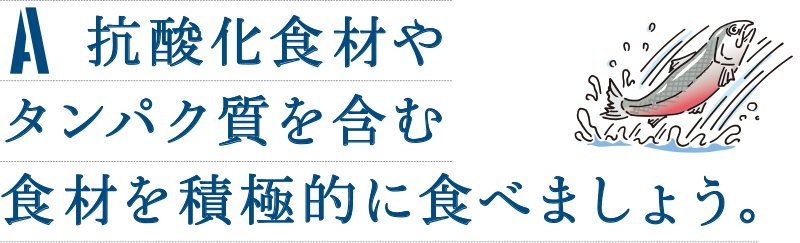
食生活で考えると、体の酸化を防ぐ「抗酸化成分」を摂ることがポイントになります。抗酸化成分にはさまざまな種類があり、緑黄色野菜や果物などに多く含まれていますが、肉体疲労にはアスタキサンチンという成分が有効です。鮭や鱒などに多く含まれる赤い色素ですね。これらの魚は産卵の際に上流に上りますが、激しい動きによって活性酸素が過剰に発生します。筋肉疲労を起こさないよう、筋肉中に蓄積されたアスタキサンチンを活用して活性酸素を除去しています。遡上の時期になると鮭の体が赤く変わるのはそういう理由なんです。
また、筋肉は傷つけば再生するメカニズムを持っていますので、筋肉の材料となるタンパク質(アミノ酸)が必要になります。通常、成人だと自分の体重×1.1gの量が必要と言われていますが、年齢を重ねるにつれ必要なタンパク質は増え、自分の体重×1.5gを摂取するとちょうどいいバランスと言われています。肉や魚、大豆などをしっかり食べて補うのが理想ですが、それだけの量を食べるのが難しい方は、アミノ酸サプリメントで補給すると効率的です。
こういったアミノ酸は血液を介して全身に運ばれていきますので、青魚に含まれるDHA・EPAといった成分で血流をスムーズにすることも意識しておくことが大切です。
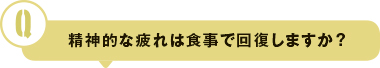
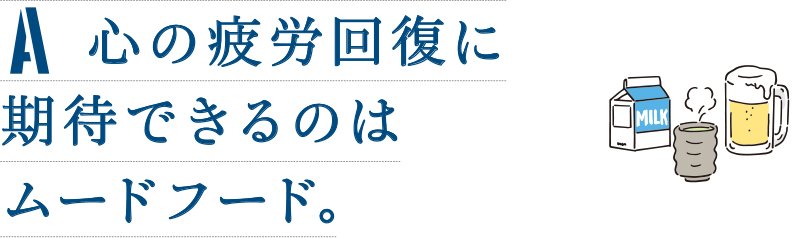
精神の疲れは、肉体の疲れとも連動しています。たとえば、これまで一生懸命頑張ってきたことが失敗した時、疲労感は増し、肉体が思うように動かないことってありますよね。その状態が続くと、日常的に動かなくなり、ますます疲れやすい体になってしまいます。どうすればいいかと言うと、メンタルを安定させることが求められるわけですが、その効果が期待できるものとしてハーブやミルクペプチドといった「ムードフード」が挙げられます。
また、ストレスに強くなるためにはマイペースで生きること。悩みがあってもあっけらかんとしておくことで、心身の疲れもとれやすくなり、毎日もきっと楽しくなるでしょう。
この記事を監修された先生

早稲田大学規範科学総合研究所ヘルスフード科学部門 部門長。長年、企業や大学の研究機関で食の安全や健康食品の研究に従事。食べ物がいかに体に作用するかを分かりやすく解説。






 Members Club
Members Club



















